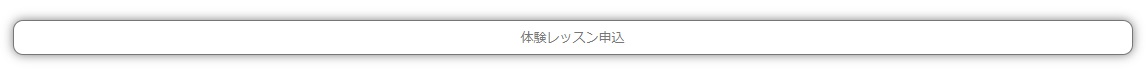歌ってみた やり方 録音方法
コンテンツ
- 1 「 歌ってみた 」の やり方 ~録音に必要な機材~
- 2 「 歌ってみた 」の やり方 ~録音手順1 マイクのセッティング~
- 3 「 歌ってみた 」の やり方 ~録音手順2 DAW(Cubase)の設定~
- 4 「 歌ってみた 」の やり方 ~録音手順3 録音レベル~
- 5 「 歌ってみた 」の やり方 ~録音手順4 分割録音~
- 6 「 歌ってみた 」の やり方 ~録音手順5 データの確認~
- 7 「 歌ってみた 」の やり方 ~録音手順6 書き出し~
- 8 「 歌ってみた 」の やり方 ~録音データの送付方法~
- 9 「 歌ってみた 」の やり方 ~録音方法まとめ~
- 10 「 歌ってみた 」の やり方・録音方法 ~歌い手のお悩み相談~
初心者のために「歌ってみた」のやり方、録音から依頼をするまでの手順をご説明します。
※パソコンでの対応方法です。またDAWはCubaseを基に説明いたします。
「 歌ってみた 」の やり方 ~録音に必要な機材~
歌ってみたを行うのに必要な機材はこちらです。
■必須
パソコン
DAW(録音ソフト)
オーディオインターフェース
マイク
マイクスタンド
ケーブル
ヘッドフォン
■あると良い
ポップガード
リフレクションフィルター
以下、おすすめの機材を紹介していますので、参考にしてみてください!
↓「歌ってみた」おすすめ機材
 |
「歌ってみた」おすすめ機材-歌ってみたを始めたい方におすすめの機材- |
| Three Oak DTM Schoolがおすすめする、「歌ってみた」を始めてみたい方に向けたおすすめ機材を紹介する「 歌ってみた おすすめ機材 」のページです。価格も比較的抑えめで、かつ実用的で使いやすい機材を掲載していますのでこれから「歌ってみた」を始めてみたい初心者の方は参考にしてみてください。 |
※スマホ録音でも可能ですが、音質は悪くなってしまいます。
ただし、スマホに接続できるマイクを使用するなど、やり方を工夫すればこの悩みも解消できます。
上記リンクにてスマホ用マイクも紹介しています。
「 歌ってみた 」の やり方 ~録音手順1 マイクのセッティング~
まずはマイクの高さと距離を調整しましょう。
理想としては拳ひとつ分を離し、口と鼻の間くらいにマイクが来るように調整しましょう。
この時、マイクの指向性がある場合は、その方向や角度もしっかりと設定する必要があります。
ハンドマイクで録音するやり方では、この距離を一定に保つことが出来ないので
マイクスタンドを使いポジションを固定することが重要です。
口とマイクの間にポップガード、マイクの後ろにリフレクションフィルターをセッティングしましょう。
※ポップガードが無いと呼吸音などが強調されます。
※リフレクションフィルターが無いと部屋鳴りなどが強調されます。
「 歌ってみた 」の やり方 ~録音手順2 DAW(Cubase)の設定~
サンプリング周波数と解像度の確認をします。
よほどのこだわりがある場合は除き、一般的なCDや配信楽曲と同様の44,1kHz/16bitをおすすめします。
※サンプリング周波数と解像度にはいろいろな意見もありますが、こちらを推奨しています。
※オフボデータを貼った後に変更する場合、テンポやピッチに変化が出る場合もありますので先に行いましょう。
Cubaseの場合、
プロジェクト>プロジェクト設定>録音ファイル形式
から設定を変えることが出来ます。
オフボ音源(カラオケ)を張り付け準備をします。
最初に空白がある場合も削らずそのままにしておきましょう。
Cubaseの場合、ミュージカルモードと言うプロジェクトに曲のテンポを合わせる機能が搭載されているので、
オフボ音源(カラオケ)を再生してテンポやキーに違和感がある場合は、オフボデータをダブルクリックで開き、
上部にある音符マークのミュージカルモードをオフにしてください。
自身の声を録音するトラックも立ち上げましょう。
その際、必ずモノラルトラックで立ち上げるようにましょう。
Cubaseの場合、そのトラックのモニタリングボタンを押すと自分の声が聞こえるようになります。
また、自分の声をモニタリングする際、実際に歌っている声と聞こえてくるが遅れる場合は、
オーディオインターフェースのバッファ/レイテンシーを調整しましょう。
Cubaseの場合、
スタジオ>スタジオ設定>オーディオシステムのひとつ下のご自身の所有するインターフェイス名>コントロールパネル
こちらで調整できます。
オーディオインターフェイスによって記述は異なる場合がありますが、
そのコントロールパネル内のバッファ/レイテンシーを限りなく0に近づけてください。
※0に近づけたことによって録音中にノイズや音飛びがある場合は、少し上げてください。
「 歌ってみた 」の やり方 ~録音手順3 録音レベル~
録音レベルが小さすぎると、ミックスをする際に適正レベルに持ち上げた時にノイズが増幅されます。
特にしっかりとしたレコーディングスタジオではなく、自宅で録る場合には細心の注意が必要です。
少し簡単に説明すると、録音する際に入ってしまうノイズの量は環境にもよりますが一定で入ってしまいます。
適正なレベルで録音されていればノイズはさほど気になりませんが(家の外がうるさい、などは除きます)、
小さいレベルの場合、ミックスするのに適したレベルまで大きくした場合、
ノイズもその分大きくなってしまいます。(図参照)
そうするとやはりキレイな音声でのミックスは難しくなってしまいます。
そのため適正レベルで録音することが必要になってきます。
では適正レベルとは何でしょう?
厳密に言うと異なる部分はありますが、これも簡単に説明すると「クリップ」させない、と言うことになります。
クリップとは、音を再生させている時や録音している時に各トラックのレベルメーターが0dB以上になり、
ほとんどのDAWの場合赤色の目印が付いた状態のことを指します。
クリップした音は、いわゆる音が割れた状態になります。
こちらも小さく録音したものと同様、ミックスにおいてはかなりミックスの音質を低下させる原因になります。
そこで、やり方としては一番声量が出るであろう箇所、ほとんどの場合はサビだと思いますが、
サビを何回か歌ってみてマイクのボリュームを調整します。
オーディオインターフェイスの入力レベルを調整するつまみをいじって、
最大レベルの声が出た時にもクリップしないレベルに設定しましょう。
※あまりにもギリギリになるようであれば、ある程度の余裕は持っても大丈夫です。
また、以下の音には注意が必要です。
・エアコンや空調の音(基本はオフに)
・ヘッドホンからの音漏れ(レベルで調整)
・リップノイズ(口を潤すことで軽減も)
・服やアクセサリーのこすれ(服の摩擦音が少ないものやアクセサリーは外す)
・マウスのクリック音(歌っている時には触らない)
・椅子の移動音(歌っている時には触らない)
・その他、特に自宅の場合その他環境音(外の車や飛行機の音、風の音や窓の揺れる音、鳥の鳴き声など)
極力レコーディングスタジオでの録音をおすすめします。
※案外カラオケルームはノイズを拾いやすいので、あまりおすすめできません。
「 歌ってみた 」の やり方 ~録音手順4 分割録音~
最初から最後まで一節で歌えてしまえば問題ないですが、難しい曲や一節で歌いにくい曲などもあると思います。
特にボカロ曲を歌う場合、ブレス(呼吸)のタイミングによってはなかなか一節では歌いにくいものもありますよね。
その際は無理せずに分割して録音しましょう。
いくつか方法はありますが、オーソドックスなものとしてはABサビなどのパートごとに歌い分ける方法です。
パートごとであれば、呼吸のタイミングで一節で歌いにくい曲もカバーできます。
この時に注意したいのが、マイクの距離と声のキャラクターです。
マイクの距離が変わってしまうと、音の質も変わってしまいます。
一般的には近くなると低域が強調され、離れるほど低域が薄れていきます。
そのため、パートごとにマイクとの距離が変わってしまうと、ミックスにも影響が出てきてしまいます。
よくテレビなどで見る「バミリ」を用意するのも距離を保つには良い方法です。
キャラクターも重要な要素です。
もちろんあえてそれを行うことで原曲に近い雰囲気やメリハリを付ける、と言うことはありますが、
例えばサビで一節で歌うのが難しい場合に前後半で分けるようなときに、
前半では少し鼻にかかった声、後半では喉を開いて少しオペラのような歌い方、のようになってしまうと、
極端な話別の人が歌っているように感じてしまうかもしれません。
そのため、自分自身の声のキャラクターをしっかりと把握し、
同じキャラクターで歌うことも実際には重要なファクターとなります。
また、修正や手直しをする際、個別に別日での歌い直しはおすすめしません。
理由としては、そのようなやり方の場合、音質・声のキャラクターを以前の録音状態と同じに保つのはプロでも難しいためです。
もちろん時間的な制約で難しいこともあるかもしれませんが、全体で歌い直すことをおすすめします。
また、歌の無い部分も少し長めに録音しておくことを推奨しています。
よく、歌い終わった直前直後でカットされる方もいますが、
歌の無い無音部分にノイズを調整するための重要な音が含まれています。
それを利用してノイズの除去を行うので、無音部分があるのかないのかで仕上がりにも大きな差が出る場合があります。
「 歌ってみた 」の やり方 ~録音手順5 データの確認~
歌詞に間違いがないか再度聞き直して確認しましょう。
特に「てにをは」の間違いや、1番/2番で歌詞が微妙に変化するものは注意が必要です。
滑舌にも問題がないか確認しましょう。
早口になって連続して歌うことが難しい場合は、分割しての再録するやり方も検討しましょう。
その他、不要なノイズが含まれていないかも確認しましょう。
ノイズの処理自体こちらでも行えますが、無いに越したことはありません。
必ず最後にご自身で聞き直して、提出しても問題ない状態か確認をしましょう。
「 歌ってみた 」の やり方 ~録音手順6 書き出し~
書き出す際にはサンプリング周波数と解像度を必ずプロジェクトで設定したものと同じもので書き出しましょう。
ここが異なってしまうと、音質にも影響を与えてしまいます。
また、多くに見受けられる書き出しが、「ボーカルデータのステレオ書き出し」です。
そもそもボーカルデータはモノラルで録音されているので(ステレオ録音はマイク2本で行います。)、
書き出し時にわざわざステレオにする必要はありません。
むしろ不要なデータになりますので、必ずモノラルで書き出しましょう。
※WAV/mono/44,1kHz/16bit推奨
また、無音部分(歌っていないけど録音はしていた部分)はカットせずにご提出ください。
ノイズの調整を行う際、とても重要な部分になりますので。
書き出す範囲も重要です。
プロジェクトの一番最初から(オフボデータ)最後までを指定して書き出しを行ってください。
原曲やオフボのデータと長さがそろっているか確認しましょう。
複数トラックで録音している場合、全トラックを書き出してしまうと容量がとても多くなってしまいます。
ボーカルの余韻やブレスが被らない箇所同士をまとめて書き出すことを推奨してます。
やり方はいくつかありますが、例えばA,B,サビをすべて個別トラックで歌っている場合
1トラック目 1A,2A
2トラック目 1B,2B,ブレイク
3トラック目 1サビ,2サビ,ラスサビ
このように分けたり、A,B,サビ自体を分けて歌っているような場合
1トラック目 1A前半,1B前半,1サビ前半,2A前半,2B前半,2サビ前半,ブレイク前半,ラスサビ前半
1トラック目 1A後半,1B後半,1サビ後半,2A後半,2B後半,2サビ後半,ブレイク後半,ラスサビ後半
このように分けたりするとデータもすっきりします。
※実際にトラックに移動しなくてもソロボタンでまとめて書き出ししても大丈夫です。
ファイル名は日本語にすると文字化けしてしまう可能性があるため、英語、もしくは日本語のローマ字表記が最適です。
録音トラックの作成時から意識しておくと良いかもしれません。
インストデータは書き出さずに、元のデータをお送りください。
キーを変更している時には、その旨を伝えてください。
「 歌ってみた 」の やり方 ~録音データの送付方法~
指定のない場合、アップローダーサイトを使っての送付が安心です。
⇒ギガファイル便
Google DriveやDoropboxでも大丈夫ですが、その場合権限の付与などを忘れないようにしてください。
「 歌ってみた 」の やり方 ~録音方法まとめ~
おおまかな流れを説明してきましたが、分からないことなどがありましたらお気軽にご相談くださいませ!
初心者向けからプロフェッショナル向けまで、歌ってみたでおすすめの機材も紹介しています
↓「歌ってみた」おすすめ機材
 |
「歌ってみた」おすすめ機材-歌ってみたを始めたい方におすすめの機材- |
| Three Oak DTM Schoolがおすすめする、「歌ってみた」を始めてみたい方に向けたおすすめ機材を紹介する「 歌ってみた おすすめ機材 」のページです。価格も比較的抑えめで、かつ実用的で使いやすい機材を掲載していますのでこれから「歌ってみた」を始めてみたい初心者の方は参考にしてみてください。 |
また、ミックスのご依頼も受け付けておりますので、気になる方はご連絡いただければと思います!
↓ご依頼はこちらから
 |
Contact |
| 問い合わせ各種はコチラから。 |
依頼方法が分からない、また不安がある方はこちらから手順をご確認ください!
↓「歌ってみた」MIX依頼方法
 |
「歌ってみた」MIX依頼-歌ってみたのミックス依頼の仕方を解説- |
| Three Oak Musicの「 歌ってみた MIX 依頼」のページです。歌ってみたけど自分でのミックスに納得がいかない、身近にミックスをしてくれる人がいない。そんな方は是非そのお悩みをお任せいただけないでしょうか?元音楽系専門学校講師がハイクオリティーのMIXをご提供いたします!ご依頼お待ちしております! |
料金の概要に関しては、下記「歌ってみた」の項を参照くださいませ!
お見積もりは上記からも承っております!
↓料金確認はこちらから
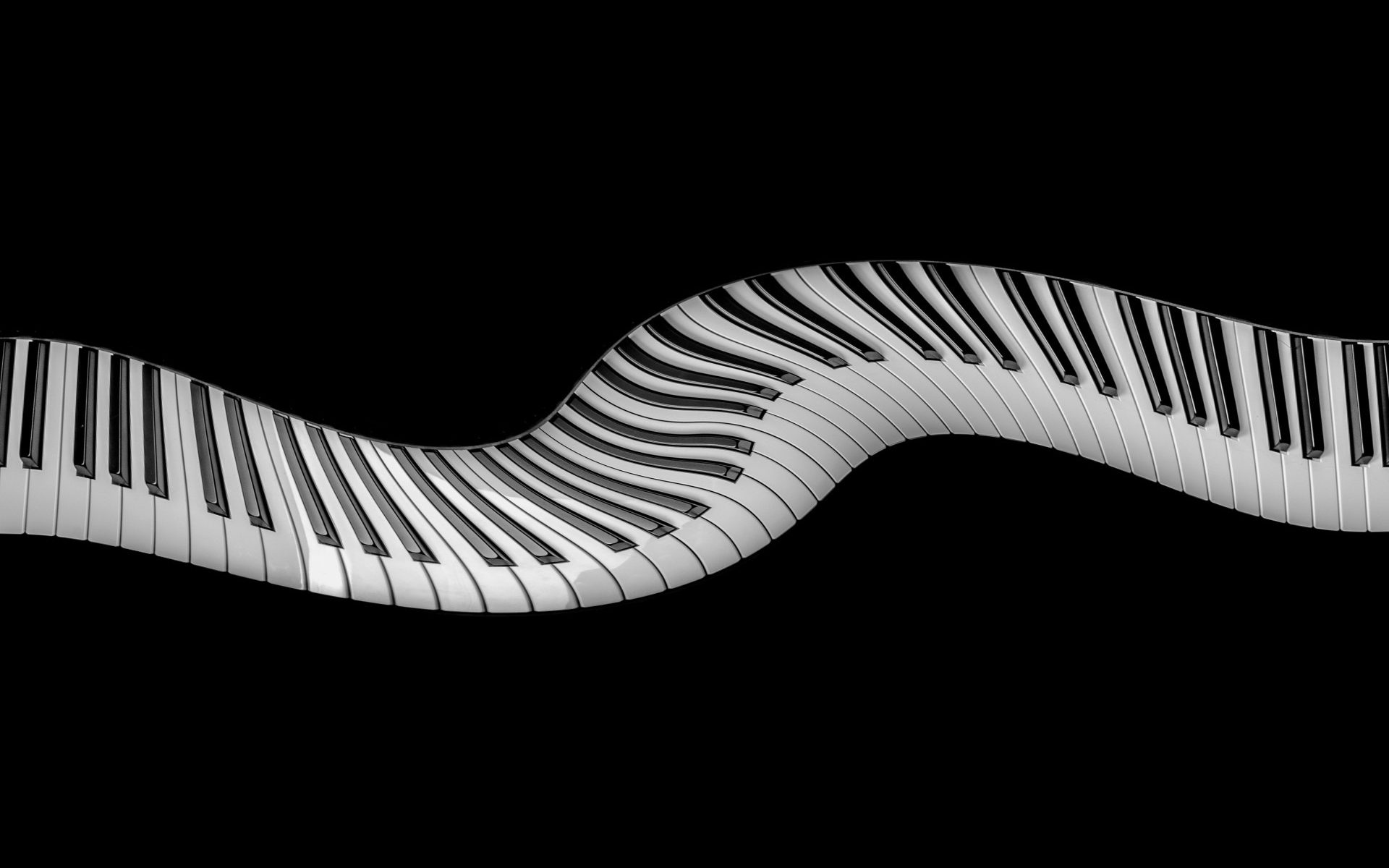 |
Price List(楽曲制作/歌ってみたMIX等料金表)-どれくらいの費用が掛かるか知りたい- |
| このページではThree Oak Music(スリーオークミュージック)の料金の情報の掲載しています。楽曲制作・効果音・ジングルなどの制作系の料金から、ミックスやマスタリング/歌ってみたのMIXの料金なども載せています。 |
「 歌ってみた 」の やり方・録音方法 ~歌い手のお悩み相談~
やり方は他にも様々ありますが、一つの参考にしていただければと思います。
音程が正確に取れない
ボーカルトレーニングを行う:正確な音程を取るためには、ボーカルトレーニングが不可欠です。声楽の基礎を学び、呼吸法や発声法をマスターすることで、音程の正確さを向上させることができます。ボイストレーナーや声楽教師と一緒に練習することで、適切な指導を受けながら技術を磨くことができます。
イヤートレーニングを行う:音程感を鍛えるためには、イヤートレーニングが非常に有効です。音楽理論やソルフェージュの基礎を学び、音の高さや関係性を正確に聴き取る力を養うことが重要です。イヤートレーニングのアプリやウェブサイトを活用して、定期的な練習を行いましょう。
ピアノや楽器の演奏を学ぶ:音程を正確に取るためには、楽器の演奏経験も役立ちます。特にピアノは、音の高さや音程の関係性を直感的に理解するのに適しています。ピアノの基礎を学ぶことで、自分の声と楽器の音を比較しながら音程を修正することができます。
レコーディングと分析を行う:録音した自分の声をじっくりと聴いて分析することは、音程の正確さを向上させるために重要です。音楽制作ソフトウェアを使用して、録音したトラックを再生しながら音程のズレや誤りを確認しましょう。どの部分が問題なのかを把握し、それに対して練習を重ねることで改善が見られるはずです。
実践を重ねる:音程の正確さは練習と経験によって向上します。定期的にライブパフォーマンスやスタジオレコーディングなどの機会を作り、実際の状況で歌い手として成長していきましょう。自信を持って歌えるようになるためには、練習と実践の両方が必要です。
リズムが正確に取れない
メトロノームを使う:リズム感を養うためには、メトロノームが非常に有効です。メトロノームのクリック音に合わせて歌うことで、定確なリズムを身につけることができます。最初はゆっくりとしたテンポから始め、徐々に速くしていきましょう。定期的な練習を通じて、メトロノームを使ったリズムの安定感を身につけることが重要です。
リズムパターンを練習する:リズムの正確さを向上させるためには、様々なリズムパターンを練習することが重要です。例えば、8分音符、16分音符、トリプレットなどのパターンを繰り返し演奏してみましょう。また、複雑なリズムパターンやオフビートの練習も取り入れることで、リズム感をより高度に磨くことができます。
ドラムトラックを活用する:リズムの正確さを練習するために、ドラムトラックを使って歌い手がリズムに合わせて歌うことが効果的です。ドラムトラックは定確なリズムを提供してくれるため、それに合わせて歌うことで自身のリズム感を向上させることができます。音楽制作ソフトウェアや音楽アプリには、多種多様なドラムトラックが収録されている場合があります。
レコーディングと分析を行う:自身の歌声を録音し、その録音をじっくりと聴いて分析することも重要です。リズムのズレや誤りを特定し、どの部分が問題なのかを把握しましょう。また、他の音楽プロデューサーやミュージシャンにフィードバックを求めることもよいでしょう。彼らの視聴者や音楽制作の経験に基づいたアドバイスは、あなたのリズム感を改善するのに役立つことでしょう。
実践を重ねる:リズム感は、練習と経験を通じて向上します。ライブパフォーマンスやスタジオレコーディングなどの機会を積極的に作り、実際の状況でリズムを鍛えることが重要です。他のミュージシャンとの共演やバンド活動に参加することで、リズム感の向上に貢献することも期待できます。
正しい発声方法を知りたい
ボイストレーニングを受ける:正しい発声方法を学ぶためには、ボイストレーニングが非常に重要です。声楽教師やボイストレーナーによる指導を受けることで、適切な発声法や呼吸法を学ぶことができます。彼らはあなたの声の特性や個別のニーズに合わせて指導を行い、声の健康と表現力を向上させるためのアドバイスを提供します。
呼吸法の練習を行う:発声の基本となる要素の一つは、正しい呼吸法です。深く腹式呼吸を行い、空気を効果的に取り込むことが重要です。呼吸法の練習を通じて、声を安定させるための基盤を作りましょう。ヨガやマインドフルネスの要素を取り入れた呼吸法の練習も有効です。
ポストウレテンツォーリングの練習を行う:ポストウレテンツォーリングは、発声の安定性と柔軟性を向上させるためのテクニックです。発声の後に続く休止や緩和の瞬間を意識し、声帯の状態をリラックスさせることで、より正確で自然な音が出せるようになります。声楽教師からポストウレテンツォーリングの方法を学び、定期的な練習を行いましょう。
レコーディングと分析を行う:自身の声を録音し、それをじっくりと聴いて分析することは、発声の向上に役立ちます。録音したトラックを再生しながら、声の安定性や明瞭さ、バランスなどを確認しましょう。問題や改善点を特定し、それに対して練習や修正を行うことで、自分自身の発声を改善することができます。
健康な生活習慣を心掛ける:発声には体全体の健康が重要です。良質な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動など、健康な生活習慣を心掛けましょう。また、喉を守るために適切な声の休養も必要です。声を酷使する前後には十分な休息を取り、声を使う前にウォーミングアップを行うことも忘れないでください。
自分に合った楽曲の選び方が知りたい
自身の音楽の好みを明確にする:まず、自分がどのような音楽ジャンルやスタイルが好きなのか、どのような感情やメッセージを表現したいのかを明確にしましょう。自身の音楽のアイデンティティや個性を理解することが、自分に合った楽曲を選ぶ上で重要です。
影響を受けたアーティストや曲を調べる:自分の音楽に影響を与えたアーティストや曲を調べ、それらの楽曲を分析しましょう。自分が好きな音楽に似た要素やスタイルを持つ曲を見つけることで、自分に合った楽曲を見つける手がかりとなります。また、そのアーティストや曲がどのようなメッセージを持ち、どのような感情を引き起こすのかを理解することも重要です。
自分の音域や歌唱力に合った楽曲を選ぶ:自分の音域や歌唱力に合った楽曲を選ぶことも大切です。自分の声の特性や強みを活かし、自信を持って歌える楽曲を選ぶことで、より表現力豊かなパフォーマンスが可能になります。また、自分の声の範囲やテクニックを向上させるために、ボーカルトレーニングを継続することも有効です。
ライブパフォーマンスやオーディションでのフィードバックを活用する:自分に合った楽曲を選ぶ際には、ライブパフォーマンスやオーディションなどの機会を活用してフィードバックを得ることが重要です。他の人の反応や意見を参考にし、自分に合った楽曲を見つける手助けとしましょう。また、音楽プロデューサーや楽曲制作の専門家に相談して、適切なアドバイスを受けることも有益です。
多様な楽曲を試してみる:自分に合った楽曲を見つけるためには、様々な楽曲を試してみることも重要です。新しいジャンルやスタイルに挑戦したり、異なる感情やテーマを持つ楽曲に取り組んだりすることで、自分の音楽の可能性を広げることができます。オリジナル曲の制作にも挑戦してみると、自分らしい楽曲を見つける手がかりになるかもしれません。
表現力の向上方法を知りたい
歌詞の解釈と感情の表現:表現力を向上させるためには、歌詞の解釈や感情の表現に重点を置くことが重要です。歌詞の意味やメッセージを深く理解し、その感情やストーリーを自分自身の経験や感情と結びつけるように心掛けましょう。歌詞の中で特に重要なフレーズやキーワードを強調し、感情を込めた表現を意識的に行うことで、聴衆に響くパフォーマンスができます。
ダイナミクスの利用:表現力を向上させるためには、音楽のダイナミクス(音量や強弱)を意識的に活用することも重要です。パワフルなパートでは力強く歌い、静かなパートでは繊細な表現をするなど、音量や強弱を使い分けることで、表現の幅を広げることができます。ダイナミクスの変化は、歌唱に感情や興奮を与えるだけでなく、聴衆により深い共感を呼び起こす効果もあります。
ボーカルテクニックの習得:ボーカルテクニックを習得することも、表現力を向上させるために重要です。例えば、ビブラート、ラン、フリルなどのテクニックを使うことで、表現の幅や繊細さを増すことができます。また、音程の正確さや声のクオリティを向上させるためにも、ボイストレーニングや声楽の基礎を学ぶことが役立ちます。
パフォーマンスの練習:表現力を向上させるためには、練習を通じたパフォーマンスのスキルも重要です。ステージでの動きやジェスチャー、表情の使い方など、全身を使った表現を練習しましょう。歌唱だけでなく、身体の動きや表情にも意識を向けることで、より一層の表現力を発揮することができます。
ライブパフォーマンスの経験:表現力を向上させるためには、ライブパフォーマンスの経験も不可欠です。実際のステージでのパフォーマンスやコンサートでの歌唱を通じて、自分の表現力を磨いていきましょう。ライブパフォーマンスでは、聴衆とのコミュニケーションやエネルギーのやり取りがありますので、それを活かして表現力を高めることができます。
インスピレーションの探求:表現力を向上させるためには、自分自身のインスピレーションを探求することも重要です。他の音楽やアーティストから刺激を受けたり、アートや文学、映画など他の表現形式に触れることで、新たなアイデアや感情を見つけることができます。自分自身の表現力を広げるために、様々なインスピレーションの源を探求しましょう。
メインメロディーにアレンジを加える方法を知りたい
ハーモニーの追加:メインメロディーに対してハーモニーを追加することで、楽曲に深みや豊かさを与えることができます。メロディーの下に和音やコードプログレッションを配置することで、メインメロディーとハーモニーが調和し、より魅力的なサウンドが生まれます。和声の基本的な原則や楽曲のキーやコード進行に基づいてハーモニーを選びましょう。
カウンターメロディーの追加:カウンターメロディーは、メインメロディーとは異なる旋律を持つパートです。メインメロディーと相互作用することで、メロディーに奥行きや複雑さを与えることができます。カウンターメロディーは、メインメロディーと調和しながらも独自のアイデアやフレーズを持つことが重要です。また、リズムや音域の異なる楽器やボーカルパートを使ってカウンターメロディーを作成することもおすすめです。
テクスチャの変化:メインメロディーにアレンジを加える方法の一つは、テクスチャの変化です。メインメロディーが出ている間はシンプルなアレンジにし、メロディーが休止している部分や間奏部分では、コード進行やリズムパターンの変化、フィルやリフの追加など、アレンジの要素を変えることができます。これにより、楽曲の流れや聴きどころを演出することができます。
ダイナミクスの変化:メインメロディーのアレンジには、ダイナミクス(音量や強弱)の変化を取り入れることも効果的です。メロディーの一部を静かに演奏するか、逆に力強く演奏するなど、音量の変化を通じてメロディーに表現力や感情を与えることができます。ダイナミクスの変化は、楽曲の興味深さやドラマティックな要素を引き立てるためにも重要です。
サウンドエフェクトやテクスチャの追加:メインメロディーにアレンジを加える方法として、サウンドエフェクトやテクスチャの追加も考慮してください。例えば、エコー効果、リバーブ、ディレイなどのエフェクトを使用してメロディーに空間感を与えたり、ストリングスやシンセサイザーのパッドなどのテクスチャを追加することで、メロディーを豊かに演出することができます。
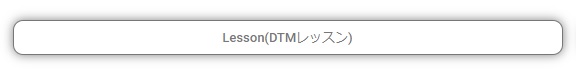
DTM Schoolのレッスン内容とスクール対応DAW紹介
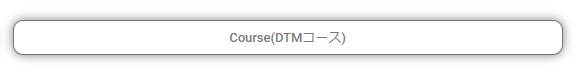
DTM Schoolのスクールレッスンカリキュラム・コース一覧

DTM Schoolのお支払い方法とスクールキャンペーン情報

DTMでの曲の作り方やDTMの操作方法を掲載
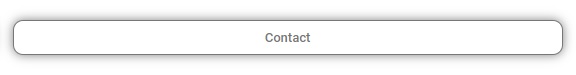
DTM Schoolへのお問い合わせ